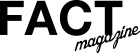今でこそ、あらゆる企業が商品を消費者に知ってもらう手段として、宣伝に知恵とお金を注ぐ時代。だが、戦前戦後の広告は薬や化粧品など限られたジャンルだけのものだった。テレビの実験放送が始まる1930年代の、ましてや刃物の新聞・雑誌広告など前例のない時代に、初代・斉治朗は目薬や胃薬、デパートの広告に混じり自社製品の広告を盛んに出した。そればかりか社内での接客用に用意していた四角いせんべいにまで替刃を模した焼印を押し、刀の部分には丁寧に砂糖までまぶし、さらには、茶碗や石鹸までネーム入りにして宣伝していたというから、いかに柔軟でユニークな発想の持ち主だったことか。
終戦後、その初代の発想力は、ポケットナイフや替刃、ハサミなどの売れ行きに拍車をかけたと言っていいだろう。当時、関市で15社余りが製造していた替刃は、フェザー(当時の貝印)が全国でも90%を占める圧倒的なシェアを誇っていた。戦後の原材料の調達や電力不足の問題もあり、1949年には替刃の生産が追いつかなくなるほどの需要量だったのだ。モノのなかった時代、品質面でも価格面でも優れていた彼らの製品は、戦前からの広告効果による知名度もあって、とにかく作るそばから売れていった。1955年には全ての包装工程を自動化し、生産量を拡大。月の生産量は300万枚にも達した。大手メーカーもこぞって替刃製造に参入したが、貝印が優位に立ち続けた。
それを裏付けるエピソードが、1957年の天皇・皇后両陛下によるご視察である。この年、岐阜市で行われた国土緑化大会の帰りに関市に立ち寄られた両陛下が、関の工場を訪れたのだ。初代はその時の感動を「光栄これに過ぎることはない」と語っている。おそらく、両陛下を工場に迎えたこの日は、生涯最高の日であっただろう。記念に工場の庭に植樹をする姿も、華々しく写真に遺されている。しかし、それで最後の大仕事を全うしたのであろうか、残念ながら翌年の1958年2月、斉治朗は病床につき、同年の7月に69歳で永眠した。
斉治朗は実に粋でユニークな男で知られていた。外出時はいつも、モーニング用の立ち襟のワイシャツにネクタイとスーツ。まるで競輪選手が乗るような細いタイヤの自転車で毎日出勤し、浄瑠璃と囲碁、パチンコを愛した。夫婦揃って株式投資が大好きだったらしい。そして困難に直面すると、荒野に芽を出す植物に学べとでも言うのか「大自然だ!」と繰り返した。「困って弱っていても仕方がない。自分さえ正しけりゃ、なんでも解決できる」という記録に残された斉治朗の言葉も、悟りの境地のように感じられる。貝印の礎には初代の、そんな心意気が息づいている。