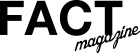〝刃物の街〟岐阜県関市に誕生した貝印。なぜ岐阜の一地方都市に、刃物で世界的な企業の本社が? 実は私たちが教科書でも学んだ「廃刀令」が深く関わっているのだ。
関市はそもそも良質の土や松炭、山々から流れ出る美しい水があり、刀鍛冶師が集まっていた。しかし1876年。四民平等を唱える明治政府の方針のもと、武士の特権である帯刀が禁じられた。困ったのは刀鍛冶師たち。生き残りをかけ、刀をつくるノウハウは、刃物の製造へと受け継がれた。
関市はそもそも良質の土や松炭、山々から流れ出る美しい水があり、刀鍛冶師が集まっていた。しかし1876年。四民平等を唱える明治政府の方針のもと、武士の特権である帯刀が禁じられた。困ったのは刀鍛冶師たち。生き残りをかけ、刀をつくるノウハウは、刃物の製造へと受け継がれた。
そんな時代の流れを読み、貝印の初代・遠藤斉治朗の兄もポケットナイフ工場を始めることとなる。弟・斉治朗も家の生活を助けるため、小学校を卒業してすぐ兄の工場で働くことに。8年の修業を終え、いっぱしのナイフ打ちとなり、結婚もし、1908年に20歳で小さな工場を始めた。
が、独立といってもそれは決して華々しいものではなかった。工員はたった2,3人。請ける仕事も下請けのそのまた下請け程度のもの。作業は薄暗い石油ランプの下、睡眠は毎日たった3~4時間。妻も心配するほど休まず働く日々だ。当時のナイフは全ての工程が手作業で、手の形が変わってしまうほどの重労働。しかし斉治朗は過酷な環境を嘆くことなく、一生懸命、誠心誠意、ナイフと向き合った。斉治朗の楽しみは、商品納品後に頂いた金で、母に土産を買って帰ることだったという。
が、独立といってもそれは決して華々しいものではなかった。工員はたった2,3人。請ける仕事も下請けのそのまた下請け程度のもの。作業は薄暗い石油ランプの下、睡眠は毎日たった3~4時間。妻も心配するほど休まず働く日々だ。当時のナイフは全ての工程が手作業で、手の形が変わってしまうほどの重労働。しかし斉治朗は過酷な環境を嘆くことなく、一生懸命、誠心誠意、ナイフと向き合った。斉治朗の楽しみは、商品納品後に頂いた金で、母に土産を買って帰ることだったという。
ほどなくして第一次世界大戦が始まり、大戦景気でナイフが飛ぶように輸出され売上げが良くなるも、1918年の終戦後にはその反動の不景気に頭を抱えることとなる。しかし当時の斉治朗は金に困りながらも、もっといい商品を作りたいと品質の向上や量産に努めていた。時には妻にヘソクリを借りてまで新しい機械を買い、研究を重ねる。その上昇志向とナイフへの思いは揺るがず、メーカーとしての地位を向上させていった。その頃に誕生したのが、ポケットナイフ史上に残る大ヒット商品「510番」だ。黒一色のシンプルなナイフは、他の業者が真似するほどよく売れた。
業界一と評されるようになってからも、現状に満足せず、斉治朗はユニークな試みで人々を驚かせた。日露戦争直後には乃木大将の似顔絵を刻印したナイフ、1923年の関東大震災後には復興ナイフを発売。当時は斬新な発想だったに違いない。また現在も発売されている、伝説の刀匠の名を冠したブランド〈関孫六〉の商標に関しても、当時の斉治朗のアイデアなのである。
近代化に邁進した明治政府により公布された廃刀令は、日本から武士という存在を葬ることになった。しかしその魂は、真面目に、丁寧に、刃物をつくり続けることに生涯を捧げた斉治朗にも受け継がれていったのではないだろうか。