

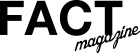

貝印最大の危機を
どう乗り越えたか。
1951年に発売を開始した使い捨ての「長柄軽便カミソリ」をヒットさせ、カミソリ王と呼ばれた遠藤繁(二代目・斉治朗)は、仕事もプライベートも順風満帆であった。〝ミス関〟にも選ばれた女性と結婚。54年には東京と名古屋の販売部門を合併して三和を設立、翌55年には大阪進出。58年に初代・斉次郎が永眠すると、繁は斉治朗の名を襲名。62年には「貝印T型(軽便)カミソリ」を発売、63年には紺綬褒章受章の名誉にまで輝いた。
言葉通り華々しいKAIグループの発展。だが、実はその裏で、東京オリンピック開催の1964年に、二代目が「生涯で最大の危機」と回想するほどの窮地に立たされていたことは、あまり知られていない。
1962年、T型カミソリの市場シェアは60〜70%となり、長柄だけで月2300万本が必要に。生産部門の三和刃物もこの急成長で自転車操業となっていた。それを心配した二代目は、古くからの町工場的組織を改革させようと実弟を送り込むが、今まで生産を一手に請け負ってきた古参の副社長や幹部との溝を深める。63年に副社長は辞任。熟練の技術者など、327人の社員中、50人以上が次いで去ることとなった。また当時、軽便カミソリのホルダーは外注で作られていたが、ホルダーの大部分を製造する会社から、値上げ要求と現金払いの通告があり、納期も滞る。64年には、もう出荷は無理という最後通告が。まさに「最大の危機」である。二代目・斉治朗は、初代とも親交が深く、信頼のおける導師、正眼寺住職・梶浦逸外老師の教えを乞うようになっていた。老師の「人間、どん底に落ちたら、それ以上落ちることはない。窮すれば、必ず転じて道が開ける」という言葉は、どれ程に斉治朗を支えただろう。また、 この危機を脱することができたのは、万一の際に備えて秘密裏に進められていたホルダー自社生産の準備があったからだ。材料の加工から最後の仕上げまで一貫した生産体制を確立するため、熟練の技術者無き後の若手だけで、満足のいくホルダーを作るのに、幾度となくテストが繰り返された。
この困難や危機を経て、グループはより強く団結した。この一件で、工場を任せきりにしてきた姿勢を改め、二代目自ら生産と販売を指導するようになる。後日、ホルダー製造会社から詫びと取引の再開を懇願されるが、二代目・斉治朗の対応は見事なものだった。「お世話になったし、そちらもお困りでしょう。ただし、社員の手前もありますから、半分だけ買い取ります。そのかわり今回のいざこざは忘れて、恨みっこなしにして下さい」と、ホルダーを半分買い取ったのだ。より良い「貝印製」への使命はさらに強い信念へと昇華され、今も貝印を支えている。
- 前の記事 FACT No.06
- 次の記事 FACT No.06




