

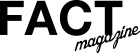

念願の一工場一品種、
生産体制が整う。
二代目斉治朗の独創的なアイデアと実行力は、貝印を大きく発展させてきた。その取り組みのひとつとして力を入れてきたものに社内報がある。1959年に販売部門の三和から『SANWA(61年から『さんわ』に変更)』、2年後に生産部門の三和刃物から『むつみ』が創刊。前者の編集には関出身の漫画家・福地泡介が参加。漫画家として独り立ちする前の仕事とはいえ、当時100名程だった全社員に配布するために、イラストから企画立案や原稿までを氏が手がけるという贅沢なものだった。64年には、浅丘ルリ子や有島一郎、渥美清までがエッセイを寄稿した号も!『さんわ』のなかでも異色の号ではあったが、福地の活躍により実現したものだったのだろう。
一方の『むつみ』では、社長宅訪問記など遠藤夫妻のプライベートも取り上げられ、斉治朗と社員を繋ぐ架け橋となった。社内報は70年に『貝』となり、91年以降、現在も『kai family』として刊行されており、会社から従業員へのPR目的だけでなく社員同士の意思疎通にも寄与している。発信することの大切さは、国内外で配布されているこの『FACT magazine』にも息づいている。
経営面では78年、小屋名の第一工場が完成する。カミソリの生産性と品質の向上を目指して建設したこの工場の稼働によって、包丁、ツメキリ、ハサミ、カッター特殊刃工場などと合わせて、ようやく斉治朗の念願だった”一工場一品種”体制が確立。斉治朗はこの工場や本社の他に、各地に支店や営業所を、そして主要拠点には大規模な流通センターを開設するが、当時、たくさんの地域から卸、小売りへの発送業務が行われていたため、それぞれのセンターの在庫管理は混乱。関に商品を集約したら在庫の山ということもあった。
69年から関に導入されたコンピュータ・システムも、画期的ではあったものの在庫、受注、発送管理の全てを電子化できるシステム構築するまでには、大変な苦労があった。紆余曲折を経て、新潟と関の2ヶ所に流通センターが集約され、在庫や受発注、発送を管理するコンピュータ・システムも完備され、工場から直送の体制が整った。直送体制自体は72年、関の弥生町に新築された倉庫から美容用品の直送が始まっており、関流通センターの完成によって全商品の直送体制が確立されたのは翌年のことだ。
そして1980年4月、長男・遠藤宏治が貝印刃物に入社。入社後すぐに取引先のコクヨに出向する。刃物一枚が何銭という時代に創業した貝印と、伝票1枚、帳面一冊何銭という時代から続くコクヨに通じるものがあり、そこに継承される思いを学ばせたかったと斉治朗は振り返る。長男がKAIの一員となったのは、遠藤夫妻にとっても大変喜ばしい念願の出来事であった。
- 前の記事 FACT No.09
- 次の記事 FACT No.09




